哲学 philosophy
アレテーは「外からの強制による規範遵守」ではなく、「内なる欲求や理性によって自然に生まれる行動」である点である。たとえば、勇気は無理やり奮い立たせるものではなく、恐怖を乗り越えようとする内なる意志の発露であり、正義もまた他者の目を気にして行うものではなく、自らの良心に従う行為によって生まれる。つまりアレテーは、本質的に内発性を必要とし、内発性によってのみ真の価値を持つ。 現代社会においても、この「徳と内発性」の考え方は有効である。たとえば、仕事においても「報酬」や「評価」だけを目的とする行動は、持続性を欠き、時に精神的な疲弊を招く。一方で、自らの価値観や使命感から行動する人間は、困難にも耐え、自己成長を遂げることができる。アレテーを体現する生き方は、外的な成功を追い求めるよりも、内なる充実や自己の完成を目指すものであり、それは最終的に深い幸福へとつながる。ゆえに、アレテーと内発性は切り離せない概念であり、人間がより善く、より強く、より自由に生きるための根本的な指針となるのである。
PR
思考と緊張と現象の展開 人は「緊張しない自分」を望むあまり、かえって緊張してしまうという矛盾した構造を持つものである。これは心理学や哲学の観点からも興味深い現象であり、「緊張しない」という理想状態を目指す行為そのものが、緊張を引き起こす要因となっていることが多い。つまり「緊張がない」を叶えるために人は緊張せざるを得ないという、自己矛盾的な心理構造である。 この構造は、自己観察と自己評価の仕組みに由来する。人間は自らの心身の状態を常にモニタリングし、「今の自分は緊張していないか」と確認する。この時点で既に、緊張への意識は高まり始めるのである。「緊張してはならない」と強く意識するほど、脳はその「緊張」というキーワードに過剰に焦点を当て、交感神経を活性化させる。これにより心拍数が上がり、手のひらに汗をかくなど、まさに緊張状態が生まれることになる。 この現象は「皮肉過程理論」と呼ばれる心理学理論でも説明がつく。意識的に何かを抑えようとすると、無意識の領域でかえってその対象を思い出しやすくなるというものである。「白くまのことを考えないように」と言われると、かえって白くまを思い浮かべてしまうのと同じである。「緊張してはいけない」という思考は、「緊張」というイメージを強化し、結果的に緊張を助長する。 また、社会的な期待や評価の存在も、この構造を強める。失敗を恐れ、「良い結果を出さなければならない」という思いが強いほど、緊張は高まる。これは、自己保存本能が働き、危険や失敗から自分を守ろうとする自然な反応でもある。しかし、こうした緊張は過剰になると、本来のパフォーマンスを妨げる要因にもなってしまう。 興味深いのは、多くの人が「緊張してはならない」という状態を目指す一方で、実は緊張そのものが生理的には自然で正常な反応であるという事実である。緊張は集中力を高め、注意深くさせる効果を持つ。問題はその緊張を「悪」と捉え、過度に排除しようとする心の態度であり、その過程こそが緊張の増幅装置となる。 したがって、緊張を克服するための最も有効な方法は、「緊張してもよい」という許可を自分に与えることである。緊張を排除しようとするのではなく、むしろそれを受け入れ、共存する姿勢を持つことが、逆説的に「緊張しない状態」に至る鍵となる。この構造は、禅の思想やマインドフルネスにも通じる考え方であり、「あるがまま」の自分を認めることで、余計な抵抗や不安から解放される。 「緊張しないために緊張する」という構造は、実は人間の心の成り立ちそのものであり、その矛盾を理解し受け入れることが、心の自由への第一歩となるのである。 思考によるあらゆる緊張と現象の展開
混乱により、より抽象度の高い見解が生まれる。
ある観念や概念を知ると既存の観念や概念のぐらつきから混乱が起こり、それらを統合した視点が生じる。既存の観念に対し、その他の可能性もある程度の正しさがあることに気づくとまずは混乱が起こり、それらの共通項たる視点が生まれる。
そして、より抽象度の高い見解が生まれる。
偏見は不可知領域や二律背反するような命題に対する一解釈にしか過ぎず、自己都合からその他の解釈可能性を感情的に排除しているだけ、という場合がほとんどである。
意識は、不快感から混乱を避けようとするが、こうした混乱は視点の高さを生むものであり、歓迎すべきものである場合が多い。
偏見を解く過程としての混乱
人間は混乱に直面したとき、しばしば従来の思考枠組みを超えた抽象度の高い見解に到達するものである。混乱とは、既存の知識や価値観、論理体系が適用できない状況や情報に直面し、思考や判断が揺らぐ状態を指す。その状態は一見、否定的に捉えられがちであるが、実は認識を深化させ、より高次の理解を得る契機となり得る。 人間の思考は、本来的に安定を求める。既知のパターンや概念に従うことで、判断や行動を迅速化し、安全を確保する。しかし、複雑な現象や矛盾する情報、多様な視点に触れたとき、従来の枠組みは崩れ、認知的不協和が生じる。この「分からなさ」や「説明不可能性」が、混乱という心理状態を生み出すのである。 重要なのは、この混乱を排除しようとするのではなく、むしろ受け入れ、問い直す姿勢にある。混乱は、旧来の解釈を超えた新しい構造やモデルへの飛躍を促す。哲学、科学、芸術、宗教のいずれの領域においても、根本的なパラダイム転換は、既存の枠組みの破綻、つまり混乱から生まれてきた。ニュートン力学が相対性理論に取って代わられたのも、宗教観が進化論に揺さぶられたのも、混乱が出発点であった。 抽象度とは、物事をどのレベルで捉えるかという思考の階層のことである。混乱を超えるためには、具体的・個別的な情報をいったん手放し、それらを包摂するより広い視座、より高次の構造を思考によって構築する必要がある。これは「木を見て森を見ず」の反対であり、無数の木のバラバラな情報を統合し、森という一つのまとまりを新たに発見する作業である。混乱が深いほど、その統合には高い抽象度が求められ、結果として新たな見解や概念が創出される。 また、混乱は想像力や柔軟性を引き出す要素でもある。明確な答えのない状況では、人間は直感や比喩、物語的思考を駆使し、新しい視点を模索し始める。これはアートや文学、哲学の源泉でもあり、「分からなさ」を抱えたまま表現を続ける営為そのものである。混乱があるからこそ、問いが生まれ、問いがあるからこそ、人は認識を深化させる。 現代社会は、情報過多・価値観の多様化・テクノロジーの急速な進歩といった要因から、常に混乱にさらされている。だが、それを単なるストレスや不安として処理するのではなく、「混乱の先にある新しい知」を目指す姿勢こそが、知的進化の鍵となる。混乱は、次なる抽象への入り口であり、創造性と変革の源であると言えよう。
ある観念や概念を知ると既存の観念や概念のぐらつきから混乱が起こり、それらを統合した視点が生じる。既存の観念に対し、その他の可能性もある程度の正しさがあることに気づくとまずは混乱が起こり、それらの共通項たる視点が生まれる。
そして、より抽象度の高い見解が生まれる。
偏見は不可知領域や二律背反するような命題に対する一解釈にしか過ぎず、自己都合からその他の解釈可能性を感情的に排除しているだけ、という場合がほとんどである。
意識は、不快感から混乱を避けようとするが、こうした混乱は視点の高さを生むものであり、歓迎すべきものである場合が多い。
偏見を解く過程としての混乱
人間は混乱に直面したとき、しばしば従来の思考枠組みを超えた抽象度の高い見解に到達するものである。混乱とは、既存の知識や価値観、論理体系が適用できない状況や情報に直面し、思考や判断が揺らぐ状態を指す。その状態は一見、否定的に捉えられがちであるが、実は認識を深化させ、より高次の理解を得る契機となり得る。 人間の思考は、本来的に安定を求める。既知のパターンや概念に従うことで、判断や行動を迅速化し、安全を確保する。しかし、複雑な現象や矛盾する情報、多様な視点に触れたとき、従来の枠組みは崩れ、認知的不協和が生じる。この「分からなさ」や「説明不可能性」が、混乱という心理状態を生み出すのである。 重要なのは、この混乱を排除しようとするのではなく、むしろ受け入れ、問い直す姿勢にある。混乱は、旧来の解釈を超えた新しい構造やモデルへの飛躍を促す。哲学、科学、芸術、宗教のいずれの領域においても、根本的なパラダイム転換は、既存の枠組みの破綻、つまり混乱から生まれてきた。ニュートン力学が相対性理論に取って代わられたのも、宗教観が進化論に揺さぶられたのも、混乱が出発点であった。 抽象度とは、物事をどのレベルで捉えるかという思考の階層のことである。混乱を超えるためには、具体的・個別的な情報をいったん手放し、それらを包摂するより広い視座、より高次の構造を思考によって構築する必要がある。これは「木を見て森を見ず」の反対であり、無数の木のバラバラな情報を統合し、森という一つのまとまりを新たに発見する作業である。混乱が深いほど、その統合には高い抽象度が求められ、結果として新たな見解や概念が創出される。 また、混乱は想像力や柔軟性を引き出す要素でもある。明確な答えのない状況では、人間は直感や比喩、物語的思考を駆使し、新しい視点を模索し始める。これはアートや文学、哲学の源泉でもあり、「分からなさ」を抱えたまま表現を続ける営為そのものである。混乱があるからこそ、問いが生まれ、問いがあるからこそ、人は認識を深化させる。 現代社会は、情報過多・価値観の多様化・テクノロジーの急速な進歩といった要因から、常に混乱にさらされている。だが、それを単なるストレスや不安として処理するのではなく、「混乱の先にある新しい知」を目指す姿勢こそが、知的進化の鍵となる。混乱は、次なる抽象への入り口であり、創造性と変革の源であると言えよう。
修辞学(レトリック)は、古代アテナイの時代からある弁論・叙述の技術に関する学問で思想感情を雄弁にうまく伝達するための原理を研究する学問である。雄弁術、弁論術、説得術とも呼ばれることがある。こうした修辞技法は分野間を横断して利用されていった。
修辞学と詭弁と生兵法 アリストテレスによる弁論術(修辞学)では、以下の三種類が挙げられている。 「話し手の人柄にかかっている説得」 「聞き手の状態・感情に訴える説得」 「言論そのものにかかっている説得」 修辞学、すなわちレトリックとは、言葉を用いて他者に影響を与える技法や学問体系を指す。古代ギリシャにおいては、弁論術として発展し、哲学や政治、教育において極めて重要な位置を占めていた。レトリックは単なる美辞麗句や装飾ではなく、相手の心に届く言葉を選び、適切な場面で効果的に用いるための知恵である。 レトリックは、言葉の選び方、表現方法、構成の工夫などを通じて、説得力や印象を高めることを目的とする。古代ギリシャのアリストテレスは『弁論術』の中で、説得のための三要素として「エートス(話し手の人格や信頼性)」「パトス(聴き手の感情への訴え)」「ロゴス(論理的な筋道)」を挙げた。これらを適切に組み合わせることによって、言葉は人々を動かし、共感や行動を引き出す力を持つ。 レトリックにはさまざまな技法が存在する。たとえば「比喩(メタファー)」は、異なるものごとを結びつけることでイメージを鮮明にする。「反復」は重要な言葉を繰り返すことで印象を強め、「対比」は異なるものを並べて違いを際立たせる。「倒置」や「省略」も、文章のリズムや緊張感を生み出す効果を持つ。これらの技法は、日常会話から広告、演説、文学作品に至るまで広く活用されている。 また、レトリックは単に「説得する」ためだけの技術ではない。聴き手や読み手に対して「美しさ」や「快さ」を届ける役割も果たす。人間は単なる情報ではなく、意味づけされた言葉、美しく響く言い回し、心に残る表現に深く反応する。よって、レトリックはコミュニケーションを豊かにし、他者との関係性を深める文化的な営みでもある。一方で、レトリックはその強力さゆえに、悪用される危険性も伴う。事実を歪めたり、感情に訴えかけて合理的な判断を曇らせたりすることも可能である。プロパガンダや詐欺的な言説は、レトリックの負の側面の一例である。そのため、レトリックは「使う力」と「見抜く力」の両面から学ぶことが求められる。聞き手・読み手としても、巧みな言葉に流されず、冷静な判断を維持する姿勢が重要となる。 現代社会において、レトリックは政治、広告、SNS、ビジネスなどあらゆる領域で不可欠な要素となっている。とりわけデジタル化が進む中、短く、強い言葉で人々の関心を引くことが重視されるようになり、レトリックの重要性はますます高まっている。キャッチコピーやプレゼンテーション、動画コンテンツにおいても、印象に残る言い回しや心を動かすストーリーが重視されるのはそのためである。レトリックは、人間の知性と感性の両方に働きかける技法であり、効果的なコミュニケーションには欠かせない要素である。正しく学び、正しく使うことこそが、言葉を通じて世界を変える力となるのである。
修辞学と詭弁と生兵法 アリストテレスによる弁論術(修辞学)では、以下の三種類が挙げられている。 「話し手の人柄にかかっている説得」 「聞き手の状態・感情に訴える説得」 「言論そのものにかかっている説得」 修辞学、すなわちレトリックとは、言葉を用いて他者に影響を与える技法や学問体系を指す。古代ギリシャにおいては、弁論術として発展し、哲学や政治、教育において極めて重要な位置を占めていた。レトリックは単なる美辞麗句や装飾ではなく、相手の心に届く言葉を選び、適切な場面で効果的に用いるための知恵である。 レトリックは、言葉の選び方、表現方法、構成の工夫などを通じて、説得力や印象を高めることを目的とする。古代ギリシャのアリストテレスは『弁論術』の中で、説得のための三要素として「エートス(話し手の人格や信頼性)」「パトス(聴き手の感情への訴え)」「ロゴス(論理的な筋道)」を挙げた。これらを適切に組み合わせることによって、言葉は人々を動かし、共感や行動を引き出す力を持つ。 レトリックにはさまざまな技法が存在する。たとえば「比喩(メタファー)」は、異なるものごとを結びつけることでイメージを鮮明にする。「反復」は重要な言葉を繰り返すことで印象を強め、「対比」は異なるものを並べて違いを際立たせる。「倒置」や「省略」も、文章のリズムや緊張感を生み出す効果を持つ。これらの技法は、日常会話から広告、演説、文学作品に至るまで広く活用されている。 また、レトリックは単に「説得する」ためだけの技術ではない。聴き手や読み手に対して「美しさ」や「快さ」を届ける役割も果たす。人間は単なる情報ではなく、意味づけされた言葉、美しく響く言い回し、心に残る表現に深く反応する。よって、レトリックはコミュニケーションを豊かにし、他者との関係性を深める文化的な営みでもある。一方で、レトリックはその強力さゆえに、悪用される危険性も伴う。事実を歪めたり、感情に訴えかけて合理的な判断を曇らせたりすることも可能である。プロパガンダや詐欺的な言説は、レトリックの負の側面の一例である。そのため、レトリックは「使う力」と「見抜く力」の両面から学ぶことが求められる。聞き手・読み手としても、巧みな言葉に流されず、冷静な判断を維持する姿勢が重要となる。 現代社会において、レトリックは政治、広告、SNS、ビジネスなどあらゆる領域で不可欠な要素となっている。とりわけデジタル化が進む中、短く、強い言葉で人々の関心を引くことが重視されるようになり、レトリックの重要性はますます高まっている。キャッチコピーやプレゼンテーション、動画コンテンツにおいても、印象に残る言い回しや心を動かすストーリーが重視されるのはそのためである。レトリックは、人間の知性と感性の両方に働きかける技法であり、効果的なコミュニケーションには欠かせない要素である。正しく学び、正しく使うことこそが、言葉を通じて世界を変える力となるのである。
アレテー・徳と内発性。

内発的動機づけ等で用いられる内発性。この内発性は「自然と内から湧いてくる」ような力やその方向・性質。内発性は徳の領域になるため、「徳の高さ」というのは「包括している対象の範囲の広さ」になる。
内発的動機づけ等で用いられる内発性。この内発性は「自然と内から湧いてくる」ような力やその方向・性質。内発性は徳の領域になるため、「徳の高さ」というのは「包括している対象の範囲の広さ」になる。
内発性とは、「自然と内から湧いてくる」ような力やその方向、性質のことです。アリストテレス的に言うとニコマコス倫理学におけるアレテー(ἀρετή )、つまり、徳です。内発性と自発性
アレテーとは、古代ギリシャ哲学において「卓越性」や「優れた性質」を意味する言葉であり、日本語では一般に「徳」と訳される。単なる道徳的な善悪の基準を超え、個々の存在が本来持つべき能力や特性を十分に発揮する状態を指す。たとえば、馬であれば速く走ること、刃物であれば鋭く切れることがアレテーであり、人間であれば「人間としての優れた在り方」が問われることとなる。
古代ギリシャの思想家たちは、このアレテーを「外から与えられるもの」ではなく、「内から湧き上がるもの」として捉えた。すなわち、アレテーは「内発性」に根ざすものである。内発性とは、行為や選択が外的な報酬や罰によるものではなく、自らの価値観や意志によって動機づけられることを指す。真に優れた生き方は、他者からの評価や強制によって形作られるのではなく、内なる声に従って磨かれるべきだという考え方である。
この視点は、ソクラテスやプラトン、アリストテレスといった哲学者たちによって深められた。ソクラテスは「善く生きる」ことの重要性を説き、それは魂の健やかさを追求することであり、自己との対話によって得られる知によって支えられると考えた。プラトンは「イデア」の世界を志向し、個人が自己の本質を認識し、理性によって導かれることこそがアレテーの実現であるとした。アリストテレスにおいては、アレテーは「中庸」によって達成されるものであり、習慣と実践を通じて人格が形成されると説かれた。
ここで重要なのは、アレテーは「外からの強制による規範遵守」ではなく、「内なる欲求や理性によって自然に生まれる行動」である点である。たとえば、勇気は無理やり奮い立たせるものではなく、恐怖を乗り越えようとする内なる意志の発露であり、正義もまた他者の目を気にして行うものではなく、自らの良心に従う行為によって生まれる。つまりアレテーは、本質的に内発性を必要とし、内発性によってのみ真の価値を持つ。
内発的とは、内部から自然に起こる、つまり外からの働きかけによらずに起こるものを意味し、その性質を持つものは内発性となる。
意識の抵抗と現実の展開はどの視点から観るのが良いのか? 現実を観る目ではない。 内側の会話、つまり内的な会話でもない。 外側でもない、内側でもない、 頭の裏側、やや上にある視点から現実を見る。 目の前の現実も、頭の中の世界も両方を見て、両方を見ずに無視するような そのような視点だ。 ある界隈では「空海」、ある界隈では三つ編みと表現されている視点だ。 第三の目の中心はまっすぐ後ろではなく上向きの後ろの延長にある、 そのような感じである。 五感で感じる今の現実でもなく、 イメージの世界でもない。 今の現実でありながら、今の直接的な現実ではない空間。 それを捉えることだ。
ソクラテス的な無知の知は、答えの行き詰まりを知っているという一種の気づきであり、哲学的な到達点の不完全性を示すようなものであるが、その先に不可知を理由に神学的な自己欺瞞に走るのは誤謬であると言わざるを得ない。
何かしら宗教的な信仰は、心底の納得ではなく、納得しようとしているという構造を持っている。
何かしら宗教的な信仰は、心底の納得ではなく、納得しようとしているという構造を持っている。
ソクラテス的無知の知とは、「自分が知らないということを知っている」という自己認識の態度である。これは古代ギリシャの哲学者ソクラテスが展開した思索の出発点であり、人間の認識には限界があることを自覚し、常に問い続ける姿勢を重視する考え方である。彼は「無知の知」によって、誤った自信や思い込みから人間を解放し、対話と探求によって真理に近づく可能性を切り拓こうとした。
この「無知の知」は、知的誠実さの象徴であり、自己の無知を正しく認識することこそが知の第一歩であるとする。一方で、現代においてしばしば見受けられるのは、不可知性を理由に信仰や独断を正当化しようとする誤謬である。つまり「分からないから○○であるはずだ」という飛躍的な主張がそれに当たる。
例えば「人間には宇宙のすべてを理解することはできない。だから神の意志によるものに違いない」という論法が典型である。この考え方は「無知であること」を認める点ではソクラテス的態度に似ているように見えるが、本質的には大きく異なる。ソクラテスは「分からないこと」を「分からないまま」に受け止め、その問いを絶えず考え続けることを尊重した。しかし、不可知を理由にした信仰の誤謬は、分からないからこそ「信じる」という飛躍を正当化し、探求を停止させるのである。この誤謬は「無知に訴える論証(argument from ignorance)」と呼ばれる論理的誤りに分類される。「証明できないから正しい」という思考は、知的怠惰を生みやすく、時に偏見や独断、非科学的信念の温床となる。科学的な態度とは、知の限界を認めつつ、現時点では分からないことを「仮に保留」し、可能な限り客観的な検証と議論を続けることである。それに対し、不可知を信仰の拠り所にする態度は、疑問そのものを封じ、対話や批判を拒絶する傾向を持つ。
また、ソクラテス的態度は根本的に「反省的」であり、「絶対に正しい」と断定することを恐れる。彼は自身を「誰よりも無知である」と認めた上で、それでも善く生きるための探求を止めなかった。つまり「知り得ない」ことを理由に、人生の問いや行動を放棄しなかったのである。これは「分からないことは分からない」と誠実に向き合う態度であり、安易な信仰や思い込みへの防波堤となる。
不可知を理由とした信仰は、時に人々に安心感や帰属意識をもたらすが、同時に思考停止や独断、他者への排他性を助長する危険性も孕む。だからこそ、ソクラテス的「無知の知」の姿勢は現代社会においてなお重要であり続ける。絶えず問いを持ち、常に「それは本当か」と自問し、対話を通じて少しずつ理解を深めていく姿勢こそが、人間の知性と自由を支える根幹である。
ゆえに、不可知を理由に信仰や断定に逃避することは、知への誠実さを失う行為であり、むしろ「分からなさ」を原動力とし、思考を続けることこそが、ソクラテス的哲学の本質なのである。
仏教上の死苦(しく)とは、死ぬ苦しみ、死の苦しみでありながら、死を迎えることからは逃れられないということを示している。四苦八苦の四苦「生老病死」のひとつである。

これは、死ぬ苦しみ、死の苦しみでありながら、死自体が経験として経験し得ないため、哲学的に考えると、「生命としての死ぬ苦しみ」、「死の苦しみ」といったものは矛盾になる。
よって、死を想起する精神の苦しみ、死に対する恐怖や死にたくないという思いから起こる精神の苦しみを意味する。死を想起し、死に恐怖を覚えたところで、何をどうすることもできない中、自己への執著から起こるのが仏教上の死苦(しく)である。
「死苦」死ぬ苦しみ
これは、死ぬ苦しみ、死の苦しみでありながら、死自体が経験として経験し得ないため、哲学的に考えると、「生命としての死ぬ苦しみ」、「死の苦しみ」といったものは矛盾になる。
よって、死を想起する精神の苦しみ、死に対する恐怖や死にたくないという思いから起こる精神の苦しみを意味する。死を想起し、死に恐怖を覚えたところで、何をどうすることもできない中、自己への執著から起こるのが仏教上の死苦(しく)である。
「死苦」死ぬ苦しみ
不足はゼロの概念がもたらす。ゼロは想像上のゼロでしかなく、本来ゼロという概念は数学的空間の中にだけあるものである。
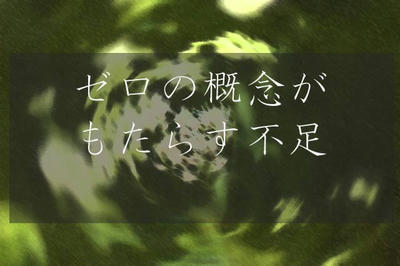
このゼロという概念が、記憶の連続性の中での記憶や想像と現実とのギャップを生む。
ゼロという概念は「無」ということを意味するが、本来自分の認識の中には「有」しかなく、空白であるはずのものに対して不足感が起こる。
これは一種の錯覚と考えることができる。
その錯覚により不足を感じることで求不得苦や愛別離苦が起こる。
自我意識、そして記憶によりゼロの錯覚が起こり、不足の判定が起こり、苦を得ることになる。
ゼロの錯覚
このゼロという概念が、記憶の連続性の中での記憶や想像と現実とのギャップを生む。
ゼロという概念は「無」ということを意味するが、本来自分の認識の中には「有」しかなく、空白であるはずのものに対して不足感が起こる。
これは一種の錯覚と考えることができる。
その錯覚により不足を感じることで求不得苦や愛別離苦が起こる。
自我意識、そして記憶によりゼロの錯覚が起こり、不足の判定が起こり、苦を得ることになる。
ゼロの錯覚
自分の内側と対話する実践。知識自体は良いですが、結局「知識の習得」を素晴らしいものとして扱い、それに逃げるということがよく起こってしまいます。人は、変化することへの恐怖から、実践することを避けています。いくら知識を増やしても内なるものと向き合うことを避けていた場合、事態は好転しません。
知識の習得という逃避と内なるものへの実践
知識の習得という逃避と内なるものへの実践
吾唯足知・吾唯知足と表現される「知足」を空性から。
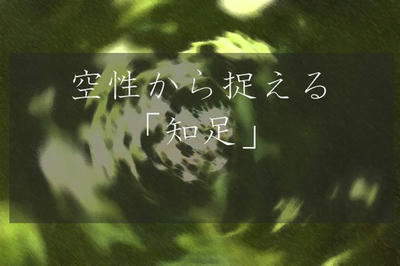
知足と空性と「充足への移動」
「足るを知る」ということを考えてみた場合、単に「満足しているということを知る」という感じで、余計な欲を起こさず、満足しなさいと命令されているように感じ、我慢を強いられるように感じる。そして、欲しくないふりしたり足りていると自分を言い聞かすような感じで捉えてしまう。それを回避するには、「欲し、得てから満足する」というプロセス飛ばし、いきなり得た状態になる、つまり充足した状態に移動すればよい。
「ある」と「ない」を抽象化すれば、全てが不確定である。そうした空性から知足を捉えると得た状態への移動、充足への移動が直感として理解できる。
「ある」と「ない」を抽象化すれば、全てが不確定である。そうした空性から知足を捉えると得た状態への移動、充足への移動が直感として理解できる。
知足と空性と「充足への移動」
確実性の度合いの問題である蓋然性(がいぜんせい)とは、「確からしさ」という意味を持つ。「おそらくそうだろう」というような確実性の度合いのことを意味する。

物事や過去の出来事に関して、それが起こるのかどうかとか、事実であるかどうかという確実性の度合い。可能性は可能かどうかの性質であり、蓋然性は確からしいかどうかを示すものになる。「確実に示そうとしても示しえないので、ある程度確からしければ」という形で、哲学的に決着がつかないようなことでも、社会の中の取り決めで利用されている概念である。
蓋然性とあいまいさ
蓋然性は確実であることを示すものではない。いかに確実らしいかということの尺度であり、社会において示し得ないものを判断する際に出てくる概念である。
物事や過去の出来事に関して、それが起こるのかどうかとか、事実であるかどうかという確実性の度合い。可能性は可能かどうかの性質であり、蓋然性は確からしいかどうかを示すものになる。「確実に示そうとしても示しえないので、ある程度確からしければ」という形で、哲学的に決着がつかないようなことでも、社会の中の取り決めで利用されている概念である。
蓋然性とあいまいさ
蓋然性は確実であることを示すものではない。いかに確実らしいかということの尺度であり、社会において示し得ないものを判断する際に出てくる概念である。
実存主義(じつぞんしゅぎ)は、普遍的・必然的な本質存在に相対する、個別的・偶然的な現実存在の優越を主張、もしくは優越となっている現実の世界を肯定してそれとのかかわりについて考察する思想。本質存在に対する現実存在の優位を説く思想。
「どうする?」というのは思考です。思考や感情というものは、ただの反応にしかすぎません。なぜどうにかしたいのかというと不快だからです。「苦」と表現してもよいでしょう。
思考を使って思考の領域を出ることはできません。厳密には限界まで達すれば端の方までは到達することはできます。その不快感なり、悲しみなり、辛い感情なりを和らげたいというようなものか、それを和らげるために苦を解消する方法を「知りたい」というのは思考。
思考や感情と私
ルサンチマン(ressentiment)

被支配者あるいは弱者が、支配者や強者への憎悪やねたみ、怨恨を内心にため込んでいること。このうえに成り立つのが愛・同情といった奴隷道徳。

実存主義の創始者と呼ばれるセーレン・キェルケゴール(Søren Aabye Kierkegaard)により確立された哲学上の概念で フリードリヒ・ニーチェは道徳の系譜(1887年)でこのルサンチマンを明確に使用しだした。ルサンチマンは、怨恨・復讐を意味する語。ニーチェは強者の君主道徳と対比して弱者の奴隷道徳は強者に対するルサンチマンと主張。
通常、ルサンチマンは怨恨や妬みなどの感情的な面で説明されることが多いが、哲学上の概念であるため、単にそうした感情を指すものではなく、怨恨感情の思考上の解決策であり、根底に奴隷道徳が存在するという意味を持つ。
被支配者あるいは弱者が、支配者や強者への憎悪やねたみ、怨恨を内心にため込んでいること。このうえに成り立つのが愛・同情といった奴隷道徳。
ルサンチマン(ressentiment)とは、「弱者による強者に対する怨恨」とするのが一般的です。怨恨の他に憤り、憎悪・非難、単純に僻みという風に説明されたりします。キェルケゴール発端ですが、ニーチェも「道徳の系譜」以降さんざん使う言葉です。ニーチェの場合は、さんざん使うというより、彼としては考えの一種の主軸になっています。ルサンチマン(ressentiment) 「善」の基礎にある怨恨感情をルサンチマンという。
実存主義の創始者と呼ばれるセーレン・キェルケゴール(Søren Aabye Kierkegaard)により確立された哲学上の概念で フリードリヒ・ニーチェは道徳の系譜(1887年)でこのルサンチマンを明確に使用しだした。ルサンチマンは、怨恨・復讐を意味する語。ニーチェは強者の君主道徳と対比して弱者の奴隷道徳は強者に対するルサンチマンと主張。
通常、ルサンチマンは怨恨や妬みなどの感情的な面で説明されることが多いが、哲学上の概念であるため、単にそうした感情を指すものではなく、怨恨感情の思考上の解決策であり、根底に奴隷道徳が存在するという意味を持つ。
今現在に集中すると起こる現象への解釈。

幅を持った意識の集中ではなく一秒前でも一秒後でもない、今現在に意識を集中していくことで、客観的な時間ではなく、この心が受け取る現象のあり方が見えてくる。
現在過去未来という時間が語られる時、客観的な仮観の世界から解釈が起こっている。しかしながら厳密に捉えた場合、そうした時間の解釈はこの内側でしか起こっていない。
「今に集中する」という場合や「現在に集中する」という場合、第三者から見て確認できない領域で、現象をどう認知しているかということや、この心は受け取る働きのみであるという部分が見えてくる。
サマタでは分離であり同時に分別の機能である自我機能が低下していく。ヴィパッサナーで集中力が上がれば、そのうち普段想起するような雑念や体感は無くなり、生滅の繰り返し、諸行無常や諸法無我が理屈を超えて体感できるようになる。
「今」に集中することと今をスタートとすること
幅を持った意識の集中ではなく一秒前でも一秒後でもない、今現在に意識を集中していくことで、客観的な時間ではなく、この心が受け取る現象のあり方が見えてくる。
現在過去未来という時間が語られる時、客観的な仮観の世界から解釈が起こっている。しかしながら厳密に捉えた場合、そうした時間の解釈はこの内側でしか起こっていない。
「今に集中する」という場合や「現在に集中する」という場合、第三者から見て確認できない領域で、現象をどう認知しているかということや、この心は受け取る働きのみであるという部分が見えてくる。
サマタでは分離であり同時に分別の機能である自我機能が低下していく。ヴィパッサナーで集中力が上がれば、そのうち普段想起するような雑念や体感は無くなり、生滅の繰り返し、諸行無常や諸法無我が理屈を超えて体感できるようになる。
「今」に集中することと今をスタートとすること
一般にある命令 ―の良し悪しは ―それが厳密に実行されたとして、その命令の中で約束された結果が生じるか、生じないかによって証明される。 道徳的な命令の場合は― ほかならぬ結果が見通されえないものであり、あるいは解釈しうるものであり、曖昧である―
深いところにある因果関係は、認識できないような領域にあるのかもしれません。それをもし捉えられたとしても、人に説明するのは難しいはずというか不可能なはず。
命令の証明 物が物として存在するためには時間が必要になります。
すごく簡単な話で、認識するためには時間が必要だからです。認識がなければ物は存在していようが、存在していないのと同じです。五感のうちのいずれかに認識されなければ、無いのと同じです。時間は一種の解釈です。人間と独立して何か次元として存在するものではありません。これは「客観的に、また社会的に考える」という歪曲された事実解釈を度外視すればすぐにわかります。
信仰、主義等々信念など選択が可能なものにしか過ぎず、朧げで曖昧で執著するようなものではない。宗教の教義、書き換え可能な信念には不完全な論理構造が潜んでいる。「確認できない対象」を推測的に示し、信じるという行為によって排他性を持ちながら混乱を避け、未来に対する不安感を妄想で打ち消すというのが宗教の構造であり、こうした教義が書き換え可能な信念の代表例となっている。
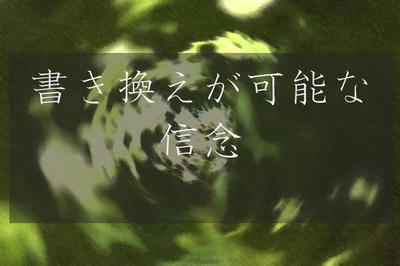
様々な証拠を持ち出しても、それすらも確実であると示し得ないという構造を持っているような不可知領域について、信仰というものによって他を排斥しているゆえに仮止めとして成り立っていると言えるだろう。
信念の書き換えと未来についての不完全な論理構造
様々な証拠を持ち出しても、それすらも確実であると示し得ないという構造を持っているような不可知領域について、信仰というものによって他を排斥しているゆえに仮止めとして成り立っていると言えるだろう。
信念の書き換えと未来についての不完全な論理構造
病の時の苦しさであり病になることから逃れられないという苦しみが仏教上の四苦八苦の病苦(びょうく)である。

病苦とは、病の時、病気の時の苦しさでありながら、そうした病に冒されることからは逃れられないという意味で「思い通りにはならない」という苦しみを意味する。可能性として病にかかるというものからは逃れられず、いくら病気を嫌おうが完全に逃れることは不可能という意味でドゥッカである。そして病気には苦しさ、痛みが伴う。生命として逃れ得ない苦しみの一つである。経典の中で四苦八苦についてはヴィナヤ・ピタカにあり、病苦について触れられているものとしては、アングッタラ・ニカーヤの健康時における健康の意気(健康のおごり)が有名である。
「病苦」病の苦しみ
病苦とは、病の時、病気の時の苦しさでありながら、そうした病に冒されることからは逃れられないという意味で「思い通りにはならない」という苦しみを意味する。可能性として病にかかるというものからは逃れられず、いくら病気を嫌おうが完全に逃れることは不可能という意味でドゥッカである。そして病気には苦しさ、痛みが伴う。生命として逃れ得ない苦しみの一つである。経典の中で四苦八苦についてはヴィナヤ・ピタカにあり、病苦について触れられているものとしては、アングッタラ・ニカーヤの健康時における健康の意気(健康のおごり)が有名である。
「病苦」病の苦しみ
自由意志はあるのか?自由意志はないのか?
そのような自由意志論という分野がある。
哲学的に見ると決定論的に自由意志はないという帰結になるが、自由意志がないとすると全ての人の意志決定に責任が無くなり、契約も犯罪の帰責も宙に浮いてしまう。
相容れなさそうな哲学と社会学の両側面から自由意志を考えていくとそうした自由意志論にそれほど意味がないことがわかる。

哲学的に考えた場合は、自分の意志は自分以外の情報の塊を発端とする自然発生的な意志にしかすぎない。しかし、社会学において自由意志を捉える時には、「『選択肢が存在していて、その選択に制約がない状態』で選ぶこと自体が自由意志とし、帰責の問題を解決している。
自由意志を哲学と社会学的帰責から紐解く
しかしながら、自由意志を語る上で理系の科学者は、無意識の反応に対して意志で抵抗できるかどうかというようなことを自由意志として捉えている。しかしそれは意識と無意識の話であって、根本的に自由意志の分野ではない。
哲学的に検討される自由意志とは、この意志自体が完全に自由であるのかどうかであり、今目の前の選択において意志決定するにあたり、経験から形成されたものすべての影響を一切受けないのかという点である。
そう考えると経験によらない意志の形成はなく、本能レベルであれば、体に組み込まれてものなので、自分が自発的にオリジナルで生み出したものではないということになる。
自由意志にまつわる理系の発想は根本的な定義や抽象度が低いということになる。
そのような自由意志論という分野がある。
哲学的に見ると決定論的に自由意志はないという帰結になるが、自由意志がないとすると全ての人の意志決定に責任が無くなり、契約も犯罪の帰責も宙に浮いてしまう。
相容れなさそうな哲学と社会学の両側面から自由意志を考えていくとそうした自由意志論にそれほど意味がないことがわかる。
自由意志と哲学的自由意志
自由意志と哲学的自由意志について。哲学的に考えた場合は、自分の意志は自分以外の情報の塊を発端とする自然発生的な意志にしかすぎない。しかし、社会学において自由意志を捉える時には、「『選択肢が存在していて、その選択に制約がない状態』で選ぶこと自体が自由意志とし、帰責の問題を解決している。
自由意志を哲学と社会学的帰責から紐解く
しかしながら、自由意志を語る上で理系の科学者は、無意識の反応に対して意志で抵抗できるかどうかというようなことを自由意志として捉えている。しかしそれは意識と無意識の話であって、根本的に自由意志の分野ではない。
哲学的に検討される自由意志とは、この意志自体が完全に自由であるのかどうかであり、今目の前の選択において意志決定するにあたり、経験から形成されたものすべての影響を一切受けないのかという点である。
そう考えると経験によらない意志の形成はなく、本能レベルであれば、体に組み込まれてものなので、自分が自発的にオリジナルで生み出したものではないということになる。
自由意志にまつわる理系の発想は根本的な定義や抽象度が低いということになる。
木を見て森を見ずとはよく言いますが、それでもまだ森しか見えていないわけですから、日本がどんな形をしているかを確認はしていません。そのようなことです。木から森を見ても、緑と茶色くらいしか見えませんが、世の中には他の多種多様な色彩があります。木を見て森を見ずという言葉をよく使う人は、個人より組織を大事にしろといったようなものを言いたいということがほとんどではないでしょうか。木から森へと視点を変える、鳥瞰図的に世の中を捉えるというのも一つの新しい視点だとは思います。しかしながら、木と言っても葉っぱから幹から、実や根までたくさんあります。それを仔細に見るといったことも忘れてはいけません。新しい眼で見る
涅槃(Nirvana)・涅槃寂静 とは、「悟り」と呼ばれる仏教の目的であり到達地点で、仏教において、煩悩を滅尽して悟りの智慧の完成の境地。

解脱と同様に表現されるが、どこかに行くわけではない。
涅槃(Nirvana)とは
涅槃(Nirvana)とは、仏教の究極的な実践目的であるが言語で示すことができない。解脱と同様に表現されるが、どこかに行くわけではない。
涅槃寂静 とは
涅槃寂静とは仏教の最終目標であり、悟りの境地としての解脱・ニルバーナ(ニルヴァーナ)であり、一切の煩悩が消え去った「静かな安らぎの境地」である。涅槃寂静とは、悟りの境地としての解脱・ニルバーナ(ニルヴァーナ)であり、一切の煩悩が消え去った静かな安らぎの境地である。仏教の最終目標。ただ言語で示すことはできない。ポジティブな表現をすれば「最高の安穏」であり、煩悩の火が消えた、一切の苦しみのない境地という意味である。
涅槃寂静
抽象度の高い哲学の主題
哲学の主題は抽象度が高い概念となる。
主題として、存在、因果、真理、本質、同一性、普遍性、観念、概念、行為、経験、世界、空間、時間、歴史、現象、数学的命題、論理、言語、知識、人間一般、理性、自由、意識、精神、自我など。倫理学的には、正義、善悪などがある。
合意のために抽象的なことを具象化する必要が生じる場合があるが、そのために元の意からは外れてしまうことが起こる。そして合意のために、観念がぐらつく。よって、内側の思考においては、合意を除外しつつ理性を保つ必要がある。
曖昧に抽象的なまま語ると妄想に見える。だからこそ語る時は具象化が必要になる。
(具象とは具体。はっきりした姿・形を備えていること)
ただ、具象化すれば意味が変わってしまうことがあり、限定が入る。
その影響で観念自体を変化させないということが重要となる。
合意と具象
曖昧に抽象的なまま語ると妄想に見える。だからこそ語る時は具象化が必要になる。
(具象とは具体。はっきりした姿・形を備えていること)
ただ、具象化すれば意味が変わってしまうことがあり、限定が入る。
その影響で観念自体を変化させないということが重要となる。
合意と具象
プロフィール
HN:
philosophy
性別:
非公開
最新記事
(07/05)
(07/05)
(06/17)
(06/07)
(05/15)
(03/18)
(03/11)
(02/27)
(02/27)
(02/26)
(02/25)
(02/13)
(02/09)
(02/08)
(02/08)
(02/07)
(02/04)
(02/04)
(02/04)
(02/03)
(02/01)
(01/29)
(01/29)
(01/28)
(01/27)
ひとこと
こちらはテスト用です。
メインサイトへどうぞ
哲学や心理学系など
哲学
哲学、倫理、道徳、心理
Dive into Myself
